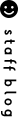2025.07.31
ペット可物件の探し方は?快適に暮らせる物件の特徴と見つけるコツ

- 「ペットと一緒に住む場所が見つからない」
- 「どうやったら優良なペット可物件を見つけられるのか?」
- 「家賃や間取りはどうすればよいか?」
このような疑問を持っている人は多いのではないでしょうか?
近年、ペット可物件は増加しており、見つけること自体はむずかしくありません。
しかし、数ある候補のなかから優良物件を見つけるにはいくつかの工夫が必要です。
本記事ではペット可物件の探し方におけるポイントや、よりよい物件を見つけるためのコツを解説します。
これからペット可物件への転居を考えている方はぜひ参考にしてください。
ペット可物件の探し方における基本的なポイント5つ
ペット可物件の探し方の基本的なポイントは以下のとおりです。
- ペットの種類や頭数にあった物件を探す
- 家賃や間取りの条件をゆるめて考える
- エリアをできるだけ広く考えて探す
- 探したうえで管理会社に交渉する
- 周辺に動物病院・ペット可な公園があるか調べる
- ペット可物件専用の不動産ポータルサイトを使う
これらを踏まえるだけで、ペット可物件を探しやすくなります。それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
ペットの種類や頭数にあった物件を探す
まずは、ペットの種類や頭数にあった物件を探しましょう。これを間違えると、入居を断られたり、住んでから不便を感じたりするからです。
たとえば小柄な犬猫が一頭であれば、間取りはワンルームでも問題ありません。
しかし、大型犬を飼育したり、複数の犬猫と暮らしたりするなら、それに応じて部屋を広くする必要があります。
また、物件が「猫はOKだが犬はNG」「飼育は1頭のみ」などと制限を設けていることもあります。
これらの背景を理解し、ペットの種類や頭数に合った物件を明確にしてから、探すようにしましょう。
家賃や間取りの条件をゆるめて考える
家賃や間取りの条件をゆるめて考えるのもポイントです。
「予算内におさまり、家賃や間取りも条件内で、かつペット可」の物件を探すのはややむずかしいでしょう。
特に都市部では、ペット可物件は全体の1〜2割程度と言われており、人気も集中しやすい傾向にあります。
そのため、家賃や間取り、築年数などを少しゆるめに考えると選択肢が広がります。
ペットの快適な生活を優先しつつ、自分の生活とのバランスに鑑みて検討してみましょう。
出典:SUMMO
また、上記のように「ペット相談」などとされている物件は比較的安い部類にあり、一度相談するのもおすすめです。
エリアをできるだけ広く考えて探す
ペット可物件を探すなら、居住エリアはある程度広く考えましょう。
居住エリアを絞り込むと、やはりペット可物件が見つかりにくくなります。
これに悩む人は少なくありません。
なかなかペット可の物件がないな
小型犬ばっかり— ずーまー (@Ks119) July 12, 2025
とはいえ、エリアを大きく変えられないケースもあります。
しかし、許容できる通勤時間を伸ばしたり、隣の駅まで検索範囲を広げたりすると、よいペット可物件にめぐり会うことも。
可能な限りエリアを広くして、広範囲からペット可物件を探しましょう。
探したうえで管理会社に交渉する
優良な物件を探したうえで、管理会社に交渉するのも有効です。
物件探しでは、物件データに書かれていることは絶対ではなく、ある程度交渉の余地があるからです。
たとえば掲載情報では「ペット不可」となっていても、交渉次第でOKになるケースも。
特に「小動物だけ」「1匹のみ」など、条件付きで許可されることも少なくありません。
もちろん「家賃を安くしたい」「敷金をなくしたい」といった交渉を持ちかけることも可能です。
惜しい物件を見つけたら、管理会社に交渉することを検討しましょう。
交渉するなら閑散期がおすすめ
管理会社に対して交渉するなら、賃貸における閑散期におこなうのがおすすめです。
一般に賃貸業界の閑散期は4月半ばから夏場までです。これは、新生活の転居が3月から4月頭で落ち着き、一時的に需要が下がるためです。
閑散期かつ部屋に空きがあれば、管理会社や大家は「多少家賃を下げたり、ペットを受け入れたりしてでも空きを埋めたい」と考えるでしょう。
この時期に入居者を得られない悩みは非常に大きいようで、
したがって、こちらの要望をとおしたうえで入居できる可能性があります。
一方で2月か4月頭までは繁忙期であり、交渉には適さない時期であることに注意してください。
また、近年では以下の動画のように閑散期狙いの引越しが増えている点にも注意が必要です。
周辺に動物病院・ペット可な公園があるか調べる
物件そのものだけでなく、周辺の環境も重要です。
動物病院や、ペットが入ってもよい公園があるか、事前に確認しましょう。
近くに動物病院があれば、急な体調不良などがあった場合でもただちに受診できるため、安心です。
また、ペットと散歩できる公園や、ドッグランのある施設が近くにあると、日々の運動やストレス解消にもつながります。
引っ越し前にGoogleマップや自治体の公園情報を活用し、実際に現地を見に行って確認しておくとよいでしょう。
周辺の施設が充実していないと、世話や移動がたいへんになるので注意してください。
ペット可物件専用の不動産ポータルサイトを使う
ペットホームウェブなど、ペット可物件専用の不動産ポータルサイトを使うのも有効です
通常の賃貸検索サイトでは、ペット可の情報は埋もれてしまいがちです。また、存在はしても登録がなされていない、条件が厳しい物件もあるでしょう。
しかし、ペットホームウェブなどでは、ペット可物件の情報だけが掲載されています。なかには、通常の賃貸検索サイトには上がっていない物件情報が見つかることも。
また、飼いたいペットの種類や大きさ、頭数なども細かく指定して検索できます。
出典:ペットホームウェブ
なかなか物件が見つからない場合は、ペットホームウェブなども利用しましょう。
【補足】ペット可とペット相談可の違いについて
ペット可物件を探す場合は、「ペット可」と「ペット相談可」の意味合いの違いに注意しましょう。
ペット可は、常識的な範囲でのペットの飼育が認められており、契約前に詳細を確認しておけばそのまま入居できます。
一方で「ペット相談可」は、種類や頭数、しつけの状態しだいで、入居を認めるか否かを判断する意味合いが込められています。すなわち、飼育の難易度が高い、頭数が多いなどの事情があると、断られるかもしれません。
「ペット相談可」を「ペット可」と取り違えた場合、「契約したものの、ペットとの入居を直前に断られる」といったトラブルがあり得ます。
これらの表記の意味合いの違いを理解しておきましょう。
より快適なペット可物件の特徴
ペット可物件を探す際は、より快適な環境を得たいと考えるでしょう。しかし、どのような環境が望ましいのか、イメージできないケースもあります。
たとえば、以下の特徴を持つ物件は、比較的快適に暮らしやすいです。
- 防音性が高く騒音の懸念が小さい
- フローリングが傷に強い素材で作られている
- ペット専用の設備がある
- 脱走経路を塞ぎやすい
これらを踏まえたうえで物件を探せば、より快適なペット可物件を見つけやすくなります。
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
防音性が高く騒音の懸念が小さい
まず、防音性が高く騒音の懸念が小さい物件が好ましいです。
ペットとともに暮らすと、鳴き声や足音が生じます。物件の構造や時間帯によっては、それがトラブルや苦情の原因になることも。
これを防ぐうえで重要なのが、防音性が高いペット可物件を選択することです。
たとえば鉄筋コンクリート造の住宅は音が伝わりにくく、トラブルを避けやすいです。また床の素材が強固かつ分厚いなら、さらに防音性は高いと判断できるでしょう。
どの程度の防音性が保たれているか、内見などで確認しておくとよいでしょう。
フローリングが傷に強い素材で作られている
また、フローリングが傷に強い素材で作られている物件もおすすめです。
鋭利な爪を持たない哺乳類や、あまり外に出る機会がない爬虫類などをのぞき、フローリング部分の損傷には注意が必要です。
損傷が激しい場合は、退去時に高額の修繕費用を請求されるかもしれません。また、一般的な木製のフローリングは容易に傷ついてしまいます。
一方で、UVコーティングがなされている床材やクッションフロアは、比較的丈夫です。これも内見時に確認しておくとよいでしょう。
以下のようにカーペットを全面的に配するのも一つです。
出典:blue studio
ペット専用の設備がある
ペットと住めることを強みにしている一部の物件は、トリミングルームや洗い場など、ペット専用の設備を有しています。
専用設備がある物件に入居できれば、普段の清掃や世話が容易になるでしょう。
また、そのような物件はほかの入居者もペットを飼っているケースが多く、騒音などにも一定の理解があると思われます。
ペットに特化した物件があれば、優先的に検討するのがおすすめです。
脱走経路を塞ぎやすい
また、脱走経路を塞ぎやすい物件もおすすめです。
ペットと暮らすときの心配事のひとつに、自宅からの脱走が挙げられます。
GPS機能付き首輪などを用いた場合は別として、一度脱走したペットを見つけるのは簡単ではありません。そのまま再会できないケースも多々あります。
したがって、逃げてしまわないようにあらかじめ脱走経路を塞ぐのが大切。
そのうえで、そもそも窓の数が少なかったり、敷居などを設置しやすい住宅のほうが、ペットとの暮らしには向いています。
また、以下のように「玄関扉を空けてもまだ建物内になっている」構造の物件なども、脱走のリスクが低いです。
この前のくるちゃん脱走の件で愛猫がいなくなってしまう恐怖と悲しさを知り、奮発してエアタグ買ってつけました。
私のお小遣いです。
万が一に備えて…後悔しないように。
まず脱走させないこと。
脱走したらもう帰ってこないと認識してます。 pic.twitter.com/KezkilfPPu— ゆっきーꕤ︎︎ꕤ︎︎ (@yukkii0724) June 4, 2023
万が一に備えて、GPS機能がついた首輪を利用するのも一つ。
ペット可物件に引っ越す前にかならずやっておくべきこと
ペット可物件が見つかって引っ越す前には、かならずやっておきたいことがいくつかあります。
- ペットの飼育条件をきちんと確認する
- 鳴き声やにおい対策に関して考えておく
- ペット用品に不足があれば買い足しておく
- 新しい家賃と飼育費用に無理がないか計算する
- 脱走対策に役立つグッズを集める
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
鳴き声やにおい対策に関して考えておく
鳴き声やにおいの対策も考えておきましょう。
鳴き声は、時として騒音となり、隣人とのトラブルを招きます。
においに関しては、主に退去時のクリーニング費用を発生させないうえで大切です。
空気清浄機、脱臭スプレーなどを活用し、においが残らないようにしましょう。
特に空気清浄機は強力です。
近年ではペット向けの空気清浄機も発売されています。
ペット用品に不足があれば買い足しておく
また、ペット用品に不足があるなら買い足しておきましょう。
たとえば、室内の広さに応じたケージや、トイレの増設、引っかき防止のためのマットなど、新しい環境に合わせた用品が必要になるケースもあります。
なお、すでに使用しているペット用品があるなら、新調するよりも引き続き使用するのがおすすめ。
ペットにとって自分の匂いが染み付いたペット用品は安心感を得られるものであり、環境の変化があっても多少精神的に安定しやすくなります。
脱走対策に役立つグッズを集める
引っ越し直後は、ペットが新しい環境に慣れておらず、脱走や隠れ行動に出るリスクが高くなります。
飼い主自身が新居に慣れていないので、普段よりも危険性は高くなるでしょう。
特に窓や玄関の開閉時には注意が必要です。
脱走防止ゲートやネットなどを設置しておくと安全性が高まります。
また、万が一の脱走に備えて、首輪に連絡先を記したタグをつける、マイクロチップを装着するなどの備えも実施しておきましょう。
特にマイクロチップはGPSで居場所を追跡できるため、捜索時の強力な手がかりとなるでしょう。
この前のくるちゃん脱走の件で愛猫がいなくなってしまう恐怖と悲しさを知り、奮発してエアタグ買ってつけました。
私のお小遣いです。
万が一に備えて…後悔しないように。
まず脱走させないこと。
脱走したらもう帰ってこないと認識してます。 pic.twitter.com/KezkilfPPu— ゆっきーꕤ︎︎ꕤ︎︎ (@yukkii0724) June 4, 2023
よくある質問
本記事ではペット可物件の探し方を中心に解説しました。ここではよくある質問に回答します。
- ペット可物件を契約する際のポイントは?
- 入居後にペットを飼育したくなったら?
- ペット不可を可にするには?
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
ペット可物件を契約する際のポイントは?
ペット可物件を契約する際には、特に以下を確認しましょう。
- どの種類・大きさ・頭数の飼育が認められているか
- ペット飼育によるクリーニング費用・敷金・礼金の増額はあるか?
金銭的に重要なのは礼金です。礼金は、家賃2ヶ月分以上の支払いを求められるケースが多いです。
しかし、本来は1ヶ月分までしか請求できず、それ以上の金額は入居希望者の同意を得たうえで支払っているにすぎません。
したがって、「1ヶ月分までしか払いたくありません」と言えば、礼金を安くおさえられる可能性があります。
また、一部の不動産仲介業者は必要だと言っていないものを契約に含めるなどします。
こういった巧妙な交渉術にだまされないようにしましょう。
入居後にペットを飼育したくなったら?
入居後にペットを飼育したくなったら、ペット可物件の場合はそのまま飼っても問題ありません。
ただし、細かな規則は守る必要があります。
仮にペット不可の物件に住んでいたとしても、管理会社に交渉すれば許可が下りるかもしれません。
今の賃貸の家が好きだけど、ペット不可だから出ていく覚悟で駄目元で交渉したらペット可の手続きをしてくれる事になった😭まじでお願いごとってしてみるものだなぁ🥺
— あんみつ (@anmitsuroll) March 29, 2023
このように成功したケースも多数あります。
ペット不可を可にするには?
ペット不可を可にするには、管理会社や大家に対する粘り強い交渉が必要です。
「小動物なので鳴き声が小さい」「しつけができているのでトイレの汚れなどはない」といったことをアピールすれば、入居が認められるかもしれません。なかには飼育計画を文書にまとめて送付するケースもあります。
また、敷金を増額する、原状回復費用を追加するなどの条件と引き換えに入居が認められることも。
ただし、契約書に「ペット不可」と明記されている場合は、書面による承諾を必ず取りましょう。口頭のみの許可では、トラブルになった際に証拠が残らず、不利になる可能性があります。
まとめ
本記事ではペット可物件の探し方などを解説しました。最後に重要なポイントをおさらいしましょう。
- ペットの種類や頭数に合った物件を選ぶ
- 家賃や間取りの条件は少し緩めに考える
- エリアは広めに設定して探すと見つかりやすい
- 交渉次第でペット可に変更されることもある
- 専用のポータルサイトを活用すると便利
- ペット専用施設がある住宅などは特におすすめ。
脱走対策やにおい・騒音対策も忘れずにおこなう
ペットとの暮らしを充実させるには、物件そのものだけでなく、周辺環境や入居後の備えも含めた総合的な準備が大切です。
飼い主もペットも安心して暮らせるよう、じっくりと条件を整理し、冷静に選ぶようにしましょう。
関連記事