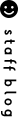2025.08.31
猫が粗相するのはなぜ?何かの理由でわざとすることがある?

- 「猫がわざと粗相しているように見えるのはなぜ?」
- 「布団やカーペットの上で突然トイレをしてしまうのはどうして?」
- 「どうすれば粗相をやめさせることができる?」
このような疑問や不安を抱えている飼い主の方は多いのではないでしょうか?
猫の粗相には「わざと」の場合もあれば、単なる失敗や体調不良が原因であるケースもあります。
だからこそ、正しい知識を持って原因を見極め、適切に対応するのが重要です
本記事では、猫が粗相をする理由を「わざと」と「失敗」に分けて解説し、改善方法や注意点を紹介します。悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。
猫が粗相をわざとする5つの理由
猫が粗相をわざとする理由はさまざですが、主に以下があげられます。
- マーキングをしている
- 「構ってほしい」と主張している
- トイレの環境を拒否している
- その場所をトイレにしたがっている
- 何らかの不満や怒りがある
いずれにせよ理由を理解し、それぞれ対応する必要があります。
以下で詳しく解説するので参考にしてください。
マーキングをしている
まず、マーキングをしている可能性があります。
猫は、自らのにおいを残すことで、テリトリーを主張する習性があります。
以下のように、猫が転がったり、体をすりつけたりするのもマーキングが目的。
特に、まだトイレのしつけが済んでいない猫にありがちです。
マーキングに関しては、これからのしつけで改善できると見込まれるので、さほど心配する必要はありません。
「構ってほしい」と主張している
粗相が、「構ってほしい」という主張を意味することもあります。
猫は、構って欲しい場合は基本的には鳴く、引っ掻くなどの方法でアピールします。
しかし、なかにはあえて粗相をすることで、その気持ちを主張することも。
したがって、しっかりと構うことで一時的には問題を解決できます。
ただ、「わざと粗相をすれば構ってもらえる」と学習させるのはいけません。したがって、根本的にトイレのしつけを見直す必要があります。
トイレの環境を拒否している
トイレの環境が悪いため、粗相をするケースもあります。
猫は清潔で手入れされたトイレを好み、汚れた状態では使いたがりません。
たとえば、前の排泄物が残っていたり、砂が古かったりすると、使用を避けます。
また、トイレ自体が狭い、遠いなどの理由から、使用を拒んでいることも。
この問題を解決するには、トイレを清掃したり、買い替えたりする必要があります。
なお、猫砂が嫌いで、シートタイプでしかトイレができないなど、特殊なケースも存在します。
その場所をトイレにしたがっている
飼い主の意思に反して、その場所でトイレをしたがっているのかもしれません。
まだしつけが済んでいない場合、猫はしつけられてトイレができないことも。
一方で、布団や砂場などが気に入れば、そこで粗相することがあります。
また、一度その場所をトイレにしようと決断したら、しばらく執着する傾向も認められます。
何らかの不満や怒りがある
何らかの不満や怒りがあって、わざと粗相するケースもあるようです。
遊んで欲しいのに無視をされた、ご飯の時間が遅れた、などの些細なことが原因になり得ます。
この場合、飼い主に原因があるのか、それとも猫がわがままなのか、切り分けて考える必要があるでしょう。
飼い主の原因なら適度にコミュニケーションを取ることが、前者なら、わがままをいうにしても、粗相でそれを表現してはいけないと、教える必要があるでしょう。
猫が粗相ではなくトイレに失敗してしまう4つの理由
猫が粗相ではなく、悪気なくトイレに失敗してしまうこともあります。その理由として、以下4点があげられます。
- トイレの場所ややり方を覚えていない
- 強いストレスが生じている
- 認知能力が低下している
- 布団をトイレだと誤認している
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
トイレの場所ややり方を覚えていない
まず、トイレの場所のやり方を覚えていない可能性があります。
特に子猫や迎え入れたばかりの猫は、まだトイレの場所を正しく把握できません。
また、単純にトイレの場所を見つけられない、ということもあるでしょう。
特に物陰や部屋の四隅など、目立たないところに設定した場合、この問題が起こりがち。
しかし、トイレの場所を変える、もしくは動線に置くなどすれば、解決されるのは時間の問題です。
強いストレスが生じている
強いストレスが生じて、トイレに失敗しているのかもしれません。
【美人猫保護4日目】食後に未消化のフード嘔吐。💩は出てるから、閉塞とかではないと思うんだけど、やっぱり環境と食事変化のストレスかな..。とりあえず明日vetだし、食事量と内容を調整して様子見。 pic.twitter.com/hjFcE90t8q
— Misa@カリフォルニア (@the_donutfamily) July 16, 2024
猫は、精神的な負荷を感じると、普段できたことができなくなるケースがあります。
たとえば、飼い主に対して攻撃になる、ご飯を食べなくなるなどの不調はありがち。
それと同様に、トイレをきちんとできなくなるケースも多々あります。
粗相が見られたら、ストレスを感じていないか確認し、可能であれば取り除くのが大切です。
認知能力が低下している
認知能力が低下したことで、粗相をする可能性もあります。
猫は一般的に、高い認知能力を持っています。これは、正確にジャンプしたり、外に出てもきちんと家に戻ってきたりする点からもうかがえるでしょう。
一方で、加齢などで認知能力は徐々に低下し、正常に判断できなくなります。
つまり、トイレではない場所をトイレだと思い、そこで粗相をするケースがあるのです。
認知症などを疑われる年齢であれば、
布団をトイレだと誤認している
また、布団をトイレだと誤認しているかもしれません。
猫は「柔らかくて、吸水性がある場所」を好んで排泄する傾向があります。つまり、そもそも布団をトイレにしやすい傾向があります。
さらに、布団には飼い主の匂いが強く染みついているため、安心感すら覚えてしまうでしょう。
トイレと布団をきちんと区別させ、粗相しないようにするのが大切です。
猫の粗相を改善する5つの方法

猫が粗相をしてしまう場合、以下のような解決方法が考えられます。
- トイレの衛生環境やサイズを見直す
- 気が済むまで構う
- トイレの場所を覚えさせる
- ストレスの原因を取り除く
- イレの数や場所を調整する
- 病気の可能性があるなら動物病院へ連れて行く
ほとんどの場合、これらいずれかを試せば問題は解決します。
それぞれ解説するので参考にしてください。
トイレの衛生環境やサイズを見直す
まず、トイレの衛生環境やサイズを見直すのが大切です。
砂が古かったり、汚れが残っていたりすると、猫はトイレの使用を極端に嫌います。
またサイズが小さいと、入りたがらないケースが出てくるかもしれません。
まずは、トイレをきちんと清掃し、できる限り清潔に保ちましょう。
また、必要に応じて大きめのサイズの猫トイレを購入する必要があります。
近年では、以下のように清掃や砂の交換を全自動でおこなうものも。
このような猫トイレがあれば、常に清潔な環境を保てるでしょう。
気が済むまで構う
気が済むまで構うことでも、粗相を改善できるかもしれません。
意識してコミュニケーションを増やしたり、いつもより綿密なスキンシップを取ったりすれば、おおむね改善できるでしょう。
ちなみに猫は甘えたいとき、このような声を出すことを覚えておきましょう。
また、声掛けやブラッシングも有効。ただ、撫でるだけでも問題ありません。
そのうえで構ってもらえないことを理由に粗相をしたなら、目を見てしっかりと叱りましょう。これを繰り返せば、「粗相をして気を引いたら怒られる」と判断できるようになります。
可愛がったり、大切にしたりするのは当然ながら重要ですが、一方でやってよいことと悪いことを区別させるのも大切です。
トイレの場所を覚えさせる
猫がトイレの場所を覚えていないなら、まずはしっかりと覚えさせましょう。
特に子猫や引っ越してきたばかりの猫は、まだ場所を正確に覚えてはいません。
家が広かったり、遠いところにトイレがあったりすれば、より粗相しやすくなります。
トイレの場所を覚えるまで、わかりやすい場所に配置するなどしましょう。もしくは、トイレに連れて行くなどの取り組みを続けるのも有効です。
基本的に、しばらくしつけを繰り返せば、たいていはトイレの場所を覚えられます。
砂の深さを調整したりすることでも、改善する傾向があります。
ストレスの原因を取り除く
ストレスの原因を取り除けば、粗相を改善できるかもしれません。
猫はストレスに対して敏感な生き物であり、粗相するレベルのものであれば、原因として以下があげられます。
- 新しい猫が家にやってきた
- 工事の騒音が非常にうるさい
- 来客があまりにも多すぎる
- 何らかの病気を抱えて苦しんでいる
これらのストレスを想定し、改善しましょう。
それだけが原因なら、対策した時点で、粗相に関する問題は解決すると見込まれます。
トイレの数や場所を調整する
トイレの数や場所を調整すれば、粗相や失敗が起こりにくくなります。
基本的にトイレの数は、猫の頭数+1が理想とされています。たとえば1頭なら2つと考えましょう。
トイレがふたつあれば、単純に失敗する確率が下がります。
また、トイレを拒否していた場合も、どちらか一方の環境を気に入ったなら、やはり問題は解決されるでしょう。
設置場所に関しては、それぞれをある程度離したほうがよいでしょう。たとえばリビングと別室、一階と二階といった分け方が考えられます。
また、以下のように猫が使いやすいように配慮したものを設置するのもおすすめです。

病気の可能性があるなら動物病院へ連れて行く
どうしても粗相や失敗を繰り返すなら、何らかの病気を発症しているかもしれません。
たとえば膀胱炎や尿路結石、腎臓病といった泌尿器系疾患は、排泄のコントロールをむずかしくします。
疾患にともなう痛みや違和感からトイレを避けてしまうことも。
高齢猫であれば認知症や運動機能の低下も原因になり得ます。
自己判断で叱ったり我慢させたりせず、早めに動物病院で診察を受けるようにしましょう。
なお、猫は腎臓疾患にかかることが非常に多い生き物です。万が一の可能性を考え、以下のチェックポイントを照合しておくとよいでしょう。
猫の粗相に関するよくある質問
本記事では、猫のトイレの粗相や失敗に関して解説しました。ここではよくある質問に回答します。
- 猫の粗相がもう限界だと感じたら?
- 粗相の汚れはどうやったら落ちる?
- 猫が布団でトイレするのは一生治らない?
- 突然粗相するようになったら?
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
猫の粗相がもう限界だと感じたら?
どうしても粗相が続き、それが飼い主にとって大きな負担となっているなら、動物病院で相談しましょう。
限界を感じるほどにトイレの悩みがあるなら、何らかの疾患があると考えられるからです。何が原因なのかわかれば、少なくとも安心できるでしょう。
また、行動改善のトレーニングを受ける手もあります。コーチングやしつけ教室でこれがなされるケースが多いので、一度探してみましょう。
粗相の汚れはどうやったら落ちる?
粗相の汚れは、一般的に洗濯などをすれば簡単に落ちるでしょう。
基本的に猫の尿はさほど色素が強いものではありません。
ただし、アンモニア臭が残りやすく、ツンとしたにおいが残留することも。
その場合は、専用の消臭、除菌スプレーを使うのがおすすめ。酸素系洗剤も、ある程度の効果があります。
アンモニア臭が残ると、猫はそのにおいがあることで「ここがトイレである」と判断するようになります。
したがって、一度ついた汚れやにおいは、丹念に落とすようにしましょう。
猫が布団でトイレするのは一生治らない?
猫が布団がトイレするのは、比較的簡単に治せます。
布団を片づけて誤認の機会を減らしたり、トイレ環境を快適に整えたりすることで徐々に治っていきます。
さらに消臭を徹底し、「布団はトイレではない」と学習させるとよいでしょう。
根気強く取り組めば、一生続く問題になることは少ないでしょう。
布団は、多くの場合猫にとって心が休まる場所であり、「粗相をするから」と取り上げるのはおすすめできません。根気強く、トイレのしつけを継続するのが大切です。
突然粗相するようになったら?
突然粗相するようになったら、以下の原因が考えられます。
- 加齢によって認知機能が低下した
- 尿路結石を発症した
- 生活リズムに何らかの変化が生じた
前触れもなく突然なら、何かしらの疾患が原因であると考えられます。
必要に応じて動物病院へ連れて行くのをおすすめします。
まとめ
本記事では、猫の粗相に関して解説しました。最後に重要なポイントをおさらいしましょう。
- 猫はわざと粗相することがある
- わざとなら、マーキングや構ってほしいという気持ちであるケースが多い
- トイレの環境が気に入らないケースもある
- 単に不満や怒りを粗相という形でアピールしていることも
- 悪気なく失敗する場合は、トイレの場所を覚えていないのかもしれない
- 強いストレスや認知機能の低下などの可能性も考えておくこと
- 改善には、トイレ環境をきれいにしたり、構ってあげたりするのがよい
- トイレの場所を覚えていないなら、再度しつけをする
- 根気よく原因を見つめ、改善を継続すれば大方は問題ない
猫の粗相は、飼い主の生活における大きな負担になり得ます。特に大事なものが汚されるなどの経験は辛いものがあるでしょう。
とはいえ、粗相も失敗もある程度の工夫で改善できます。しっかりと原因を究明し、改善されるまで対策を継続しましょう。
関連記事