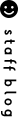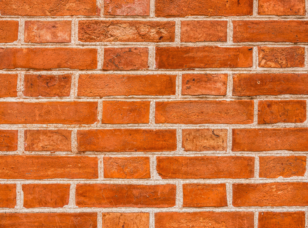2025.09.30
仲の悪い猫を仲良くさせる方法は?喧嘩発生時の対応も解説

- 「多頭飼いを始めたが、猫同士が喧嘩ばかりしている」
- 「先住猫が新しい猫を受け入れてくれない」
- 「猫たちの関係を改善する方法がわからない」
このような疑問を持っている人は多いのではないでしょうか?
仲の悪い猫を仲良くさせることは、適切な環境整備や工夫があれば、さほどむずかしくありません。
今回は、猫同士の関係改善方法から喧嘩時の対応、仲が悪くなる要因まで詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
仲の悪い猫を仲良くさせる方法
仲の悪い猫を仲良くさせるには、環境整備と工夫が必要です。
ここでは5つの方法を解説します。
- 個別にトイレや寝床を用意する
- 先住猫ファーストを心がける
- 去勢手術を受ける
- フェロモン製品を使用する
- 獣医師などに相談する
これらの方法を組み合わせて実践すれば、猫同士の関係は改善していきます。それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
個別にトイレや寝床を用意する
猫同士の関係改善には、個別のトイレと寝床の用意が必須です。
猫は本来単独生活を好む動物で、こういった場所の共有には向いていません。
トイレの数は「猫の数+1」が基本原則となります。 たとえば、3匹なら4個のトイレを設置しましょう。
猫によるトイレの取り合いは特に多い喧嘩の原因で、以下のようにそれに悩んでいる、対策しようとしている飼い主が多くみられました。
猫トイレを買ってきた
二匹いるんだけど、仲が悪くてトイレの取り合いになるのだ pic.twitter.com/Z2gTCLQexF
— よよもも (@yoyoigawa) January 11, 2019
寝床は各猫が隠れられるスペースを用意するのがおすすめです。 キャットタワーなどを飼い主が設置し、各猫のパーソナルスペースを確保しましょう。
また、ケージを持っている場合は、主に喧嘩で劣勢だったほうを一時的にケージに入れる方法もあります。
先住猫ファーストを心がける
また、先住猫ファーストを心がけるのも大切です。猫の世界には「先にそこに住んでいるほうが、すべてにおいて優先される」ルールがあるからです。
たとえば食事はかならず先住猫から与えましょう。 遊びやスキンシップも先住猫を優先的に対応し、 先住猫「自分は大事にされている」と感じさせるのが大切です。
一方で先住猫ファーストができていないと、先住猫には相当の不満とストレスが生じます。なかには、家を出ていってしまうケースも。
猫の世界のルールを重んじ、あらゆる場面で先住猫を優先させましょう。
去勢手術を受ける
基本的には、去勢手術を受けるのを推奨します。
手術により、攻撃性が低下し、喧嘩や仲違いが起こりにくくなるからです。
なお、去勢・避妊手術は、猫の意図しない繁殖を防ぐ、繁殖期の問題行動を予防するといった意味でも大切。
飼育の際は、去勢・避妊手術を受けるのを強く推奨します。
【関連記事】猫の去勢手術はいつ受けるべき?費用・手術内容・術後のケアも解説
フェロモン製品を使用する
またフェロモン製品を利用して、喧嘩しないようにするのも効果的です。
フェロモン製品とは、猫のリラックスをもたらすためのスプレーやディフューザーのこと。「フェリウェイ」が代表的なブランドとして挙げられます。
フェロモン製品を使えば、猫のストレスが軽減され、リラックスし、喧嘩する機会が減ります。
ただし注意したいのは、製品を使っても原因が取り除かれるわけではない点。根本的に解決するためには、喧嘩の理由を取り除く必要があります。
その点を踏まえて、特に喧嘩が苛烈になったときなどに、ピンポイントで使うのがよいでしょう。
獣医師などに相談する
どうしても改善しない場合は、獣医師などに相談しましょう。
一般的に猫の仲違いが改善されるのは時間の問題であり、飼い主が戸惑うほど仲が悪い状態が続くことはほとんどありません。
にもかかわらず、仲良くなれないなら、特別な指導やトレーニングが必要かもしれません。
獣医師に相談すれば、アドバイスやトレーナーの紹介を受けられるはずです。
ひどい仲違いに悩んでいる場合は、獣医師に相談してみましょう。
仲の悪い猫同士が喧嘩を始めたときの対応
仲の悪い猫のあいだでは、ときどきじゃれ合いのレベルを超えた大喧嘩が始まることがあります。
喧嘩が始まったら、怪我を防ぐためにも、以下のように対応しましょう。
- 仲の悪い猫同士の距離を取る
- 怪我などがないか確認する
- 一時的に生活のスペースを分ける
- 少しずつ距離を近づけて仲良くさせる
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
仲の悪い猫同士の距離を取る
まずは、仲の悪い猫同士の物理的な距離を取りましょう。おたがいを違う部屋に入れるのがベストです。
ただしこの際、素手を使わないようにしましょう。猫の噛みつきは深くまで達しやすく、細菌感染から重い病気になることもあるからです。
素手ではなくタオルなどで包むように持ち上げると安全です。
喧嘩をやめない場合は、うまく気を逸らしてから距離を置くようにしましょう。
おやつの袋をガサガサ鳴らしたり、お気に入りのおもちゃを投げたりするのが有効です。自動給餌器を動かして、注意を別の方向へ向けるのもよいでしょう。
また、先述のように喧嘩で劣勢だった猫をケージに入れるといった手段もあります。この場合は、ケージをタオルなどで覆い、お互い目があわないようにしましょう。
怪我などがないか確認する
喧嘩があれば、かならず怪我の有無を確認します。 猫の歯や爪は細く鋭利なため、見た目以上に深い傷になっている可能性があります。
よく体を観察し、出血などがないか確認しましょう。
また、しきりに舐めている箇所があれば、その部分を負傷している可能性があります。
目に見えないダメージを受けていることもあります。その場合は、食欲が落ちたり、やたらと隠れがったりする行動がヒントになります。
仮に怪我をしていると予想されるなら、かならず動物病院へ連れて行きましょう。
一時的に生活のスペースを分ける
さらに、一時的に生活のスペースを分けるのも大切です、しばらく顔を合わさなければ、喧嘩や相手への怒りもおさまるでしょう。
もっとも効果的なのは、お互いを別室に隔離することです。大きな喧嘩なら、しばらくは会わないようにさせましょう。
そこまでするほど大きな喧嘩でないなら、別室に隔離する必要はありません。
ただし、また喧嘩が始まらないよう、飼い主や家族で見守り、いつでも仲裁に入れるよう構えておくのが大切です。
猫同士の仲が悪くなる5つの要因
猫同士の関係が悪化する要因を理解すれば、予防や対策が立てやすくなるでしょう。 ここでは主な5つの要因を解説します。
- 初対面などで警戒心がはたらいている
- 縄張りを侵されたと認識している
- 発情期を迎えて攻撃的になっている
- じゃれあいが本気の喧嘩になってしまった
- 資源(食事・水・トイレ)の競争
それぞれ詳しく解説するので、参考にしてください。
初対面などで警戒心がはたらいている
まず、警戒心がはたらいていると考えられます。
猫は危機に瀕すると、本能的に「固まる、逃げる、戦う」という防衛反応を示します。
初対面の猫に対しては、まずこの反応を示すでしょう。
とはいえ、これは長らく共に生活していると解消される問題です。
ただし、猫同士が慣れるまでの期間は個体差が大きいです。 数週間から数ヶ月、場合によっては半年ほどかかることも。
また、初対面時に防衛本能がはたらいているにもかかわらず、無理やりコミュニケーションを取らせるのはおすすめできません。
初対面が理由で生じる警戒心は、自然に解消されるのを待ちましょう。
縄張りを侵されたと認識している
また、縄張りを侵害されたと思っているかもしれません。
猫は強い縄張り意識を持つ動物です。 特に2歳から4歳の繁殖にもっとも適した時期では、その意識はより強く発揮されるでしょう。
新しく猫を迎え入れたときや、外から帰ってきた猫に対して威嚇したり唸ったりするのは、この縄張り防衛の本能によるものです。
この場合、無理に一緒にさせるのではなく、最初は別の部屋で生活させるなど「テリトリーを区切る」工夫が必要です。
そこからは、におい交換や少しずつ距離を縮めるステップを踏むのが大切です。
そうすれば、縄張り意識が和らぎ、次第に共存が可能になるでしょう。
発情期を迎えて攻撃的になっている
また、発情期を迎えて攻撃的になっている可能性も考えられます。
発情期を迎えると、猫はホルモンの影響で行動が不安定になり、攻撃性が高まることがあります。
特に未去勢・未避妊の猫では顕著で、同居猫に対して強い威嚇や攻撃を仕掛けることも珍しくありません。
このような場合は、発情期特有の行動と割り切り、安易に叱らず距離を取って落ち着かせることが大切です。
根本的な解決には、避妊・去勢手術が必要です。先述のように意図しない繁殖などを防ぐためにも、これらに手術を受けるのを強く推奨します。
じゃれあいが本気の喧嘩になってしまった
また、じゃれあいが本気の喧嘩になってしまうこともあります。
猫同士のじゃれあいは、運動や狩りの練習といった意味があり、これ自体は問題となる行動ではありません
しかし、遊びの最中に興奮が高まり、いつの間にか本気の喧嘩に発展してしまうこともあります。
飼い主の立場としては、じゃれ合いと本気の喧嘩を見分けるのが大切です。
爪を出していない、鳴き声をあげない場合は、遊びの範疇と考えられます。
一方で、低いうなり声や唸り声を伴い、しっぽを大きく膨らませているときは本気の喧嘩と考えて問題ありません。
この場合では、猫同士を一度引き離し、これ以上大きな喧嘩にならないようにしましょう。
資源(食事・水・トイレ)の競争
猫同士が仲良くできない原因のひとつに、「資源の奪い合い」があります。食事や水、トイレ、寝床などが不足していると、それぞれが縄張りを主張し合い、衝突が起こりやすくなります。
この場合は、頭数+1の食器やトイレを用意するなど、十分な資源を確保してあげるのが大切。
また、食事は同じ場所ではなく距離を取って与えると、競争心が和らぎやすくなります。
さらに安心できる隠れ場所やキャットタワーなどの高低差を用意すると、猫たちが自分の居場所を確保しやすくなり、争いを減らすことにつながります。
猫は基本的には野性を持っており、資源を確保するには多少のけんかを躊躇しません。このような本能がはたらかないように、飼い主側が配慮するのが何よりも大切です。
仲の悪い猫たちに関するよくある質問
本記事では、仲の悪い猫たちについて解説しました。ここではよくある質問に回答します。
- 喧嘩をしているときに叱ってもよいか?
- 仲がよい・悪いことのサインは?
- ずっと仲直りできないこともある?
- 仲良しはくっついて寝る?
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
喧嘩をしているときに叱ってもよいか?
感情的に叱ったり怒鳴ったりすることはおすすめできません。
なぜなら、猫は感情的な叱責では反省せず、飼い主に対して恐怖を感じるだけだからです。どのようなケースでも、毅然としながらも冷静に対処するのが大切です
また、顕著な威嚇行動がない場合は、単なるじゃれ合いの可能性が高いです。これは特別に問題はないので、やさしく見守りましょう。
威嚇行動がある場合は、おやつで気を引いたり、手を叩いて音で気をそらしたりします。
このように冷静に対処したり、注意はしたりするものの感情的に怒鳴ったり、叱り飛ばしたりするのは避けましょう。
仲がよい・悪いことのサインは?
猫同士の関係が良好かどうかを見極めるサインは存在します。
仲がよいサインとしては、互いに毛づくろいをし合う(グルーミング)、近い距離でリラックスして寝る、遊びの中で取っ組み合っても爪を出さない、といった行動が挙げられます。
一方で、仲が悪いサインには、うなり声や唸り声をあげる、耳を伏せて威嚇する、しっぽを大きく膨らませる、近づくと逃げる・攻撃するなどがあります。
これらのサインが頻繁に見られる場合は、無理に一緒にさせず、距離を取らせるのが重要です。
ずっと仲直りできないこともある?
一度深刻な喧嘩をすると仲直りが困難になることはあります。
ただし、完全に元通りにならないケースはほとんどありません。
猫は、本来単独行動を好む動物です。
仲良しはくっついて寝る?
猫が一緒にくっついて寝るのは仲のよさを示す代表的なサインのひとつです。
猫は本来単独行動の動物なので、安心できる相手にしか体を預けません。
並んで寝たり、体を重ねたりするのは「信頼している証拠」といえます。
ただし、くっついて寝ないからといって仲が悪いとは限りません。
猫にはそれぞれの距離感があり、快適に感じるスペースは個体差があります。仲良しの関係でも、一緒に寝ることだけは嫌うといったケースも珍しくありません。
猫が持つ本来的な習性から考えれば、くっついて寝るほど仲良くなくても、さほど心配は必要ありません。
まとめ:仲の悪い猫同士も時間をかけて仲良くなれる
本記事では、仲の悪い猫を仲良くさせる方法について解説しました。 最後に重要なポイントをおさらいしましょう。
- 個別のトイレと寝床を用意し、猫の数+1の法則を守る
- 先住猫ファーストで新入り猫の受け入れをスムーズに
- 去勢・避妊手術で攻撃性を大幅に軽減できる
- フェロモン製品やプロへの相談も効果的
- 喧嘩後は段階的な再会プロセスで関係を修復
仲の悪い猫同士を仲良くさせることは、時間と根気が必要ですが不可能ではありません。ほとんどの場合で、仲良くなることが可能です。
ぜひ本記事の方法を実践して、猫たちの関係改善に取り組んでみてください。
関連記事