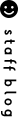2025.08.31
猫が病院に行くとどれくらいのストレスがかかる?正しい通院方法

- 「猫は病院に行くだけでどれくらいストレスを感じる?」
- 「通院時に猫が暴れたり鳴いたりするのは防げる?」
- 「診察や帰宅後に気をつけるべきことはある?」
このような疑問や不安を抱えている飼い主の方は多いのではないでしょうか?
猫は通院に対して強いストレスを感じる生き物です。しかし、キャリーバッグの使い方や診察中の対応、帰宅後の過ごし方などに配慮すれば、さほど問題ありません。
本記事では、猫を病院へ連れて行くときにストレスを与えない通院方法などを解説するので、参考にしてください。
猫を病院へ連れて行くときにストレスを与えない通院方法
猫を病院へ連れて行くときには、以下の点を意識すればストレスを与えにくくなります。
- キャリーケースに慣れさせておく
- 通院前に落ち着いた環境を整える
- 移動中は可能な限り揺らさないようにする
- タオルなどを使って目線を遮る
- フェロモン剤を使う
特にキャリーケースに慣れさせておくのは大切です。また、通院前から落ち着いた環境を用意し、移動中も気を使うなど、飼い主にはそれなりの工夫が求められるでしょう。
これらを、無理のない範囲で実施するのが、ストレスの回避に役立ちます。
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
キャリーケースに慣れさせておく
もっとも重要なのは、猫にとって恐怖の対象になり得る、キャリーケースに慣れさせておくことです。

キャリーケース内部に入り、遠いところへ出かけるのは、猫にとって大きな負担です。
以前にも病院へ行ったことがある場合、注射のトラウマを思い出すかもしれません。
これを防ぐために、普段からキャリーケースに短時間入る練習などをして、慣れさせるのが大切。
最初は数分程度から入れて、最終的には長らくいられるようにしましょう。キャリーケースに慣れるだけで、通院はかなり楽になります。
怖がらないようになるまで、時間がかかるかもしれません。しかし、根気強く練習を続ければ、たいていの場合で改善するでしょう。
通院前に落ち着いた環境を整える
また、通院前に落ち着いた環境を整えるのも大切です。
家の中が騒がしいと、出発前から猫が警戒してしまいます。
穏やかな音楽を流したり、部屋を少し暗めにして、猫が安心できる空間を作ってあげるのがポイント。さらにコミュニケーションを取ったり、可愛がったりすると、多少は落ち着くでしょう。
ちなみに、猫のためのヒーリングミュージックを使う方法もあります。
528Hzや888Hzの周波数を持つ音楽は、猫にとって癒しになります。YouTubeで簡単に見つけられるので、一度聞かせてみましょう。
一方で通院前に大きな音を立てたり、急に捕まえたりしないよう注意しましょう。特に捕まえられるだけで不安を感じてしまう猫は多いです。
移動中は可能な限り揺らさないようにする
移動中は、可能な限り揺らさないようにしましょう。
猫は揺れに対して敏感であり、自動車のエンジンの揺れが伝わると不安が強まります。
キャリーケースを固定したり、毛布やタオルなどを緩衝材にしたりして、振動が届きにくくしましょう。
また徒歩で移動する際も、なるべく安定した姿勢と角度で運ぶようにしましょう。
可能な限り、段差や坂道も避けたいところです。
なお、この際もヒーリングミュージックを聴かせて落ち着かせる方法が有効かもしれません。
タオルなどを使って目線を遮る
また、タオルなどを使って目線を遮るのも大切です。
移動中の景色や人の行き来、自動車の排気音など、外部からの刺激は猫にとって大きなストレスになります。
キャリーケースにタオルやブランケットをかけて視界を遮ると、猫は落ち着きやすくなります。
暗くて静かな環境をつくることで、自宅の寝床にいるような安心感を与えられます。
また、キャリーのなかで粗相をしてもタオルが吸収してくれるでしょう。
ただし、夏場は熱がこもりやすいため、あまりにもスキがない包み方をするのは危険。熱中症などを避けるためにも、この点には注意しましょう。
フェロモン剤を使う
どうしても精神的に安定しない場合は、フェロモン剤の使用も検討しましょう。
ここでいうフェロモン剤とは、猫が精神的に落ち着く成分を混ぜたリキッドのこと。

キャリーケースの内側やタオルにスプレーすることで、猫の不安を和らげることができます。
特に神経質な性格の猫や、過去に通院で強いストレスを経験した猫におすすめ。
動物病院でも推奨されることが多く、比較的手軽に取り入れられる方法のひとつです。
日頃からキャリーにフェロモン剤を使い、ポジティブな体験と結びつけておくと、効果が高まるでしょう。
なお、一般に販売されているフェロモン剤には、中毒などのリスクはほとんどありません。
猫が診察中にストレスを感じないためのポイント

猫は、通院中だけではなく診察中(待合室から診察室で過ごすあいだ)にも一定のストレスを感じます。特に注射の瞬間などは、飼い主も気の毒に思うほどの負担がかかるでしょう。
少しでも負担を減らすため、以下のポイントを意識しましょう。
- キャリーケースを高い場所に置く
- タオルなどで体を包む
- 可能であれば体を撫でる
- 抗不安剤の投与を検討する
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
キャリーケースを高い場所に置く
待合室にいる際は、キャリーケースを高い場所に置くのが有効です。
先述のとおり、人の行き来などが見えると、猫には大きなストレスがかかります。
そこに大きな音や、注射などのトラウマが重なれば、相当な負担になるでしょう。
しかし、キャリーケースを高い場所に置けば、目線が遮られ、ある程度ストレスを軽減できます。
仮にそのようなスペースがあるなら、動物病院に許可を取ったうえで利用しましょう。
タオルなどで体を包む
待合室にいる、もしくは診察中は、タオルなどで体を包むとよいでしょう。
暗くて狭い空間にいる方が安心する猫にとって、身体を包まれる感覚は「隠れ場所」を得るのと同じような効果をもたらします。
また、飼い主の手の温かさが伝わる部分もあるでしょう。
一方で、タオルで包むことが、診療のさまたげになる場合もあります。あくまでも獣医師の指示にしたがうようにしましょう。
また、使用するタオルに関しては、猫や飼い主の匂いが染み付いたものを使うのがおすすめです。
可能であれば体を撫でる
可能であれば、体を撫でるなどして猫の精神状態を落ち着けましょう。
特に首周りや背中などを撫でられると、リラックスしやすいです。同時に声かけをすれば、さらに安心できるでしょう。
ただし、待合室では、キャリーケースの外に出すのがむずかしいかもしれません。その場合は、脱走を防止するなどの観点から、外には出さないようにしましょう。
動物病院によっては、極端に怖がる猫に関しては、個室を用意してくれるなどの対処があるかもしれません。
なお、脱走を防ぐためには、GPS追跡機能が搭載された首輪、Airtagなどを利用するのがおすすめです。
抗不安剤の投与を検討する
必要に応じて、抗不安剤の投与を検討しましょう。
抗不安剤とは、精神的なストレスをやわらげるための薬品です。

アンキシタンという薬が幅広く使われているようです。
これは、猫の性格やストレスの度合いに応じて処方されるもの。無理な診察によるトラウマを避けるためにも、導入を検討しましょう。
ただ、抗不安剤には一定の副作用があると考えられ、猫の健康が損なわれる可能性もあります。
この点を踏まえたうえで、投与するかどうか考えましょう。
猫が病院から帰ってきたときにやってはいけないこと

猫が病院から帰ってきたとき、いくつか「やってはいけないこと」があります。
- 到着後に飼い主はすぐに外出しない
- 怒っているときに手を近づけてはいけない
- 基本的に寄り道はしない
これらの行動だけは避けるようにしましょう。
到着後に飼い主はすぐに外出しない
病院から帰ってきてすぐに外出しないようにしましょう。
すぐに飼い主が外出してしまうと、猫は強い不安を再度感じます。
しばらくは、猫のようすが落ち着くまでそばにいるようにしましょう。もしくは、家族に面倒を見てもらうのがおすすめです。
ただし、病院から帰ってきた時点で、安心していつもどおりに過ごせるケースもあります。このあたりは、猫のようすを見ながら判断しましょう。
怒っているときに手を近づけてはいけない
病院から帰ってきた段階で、猫が精神的に不安定になりすぎ、怒ってしまうことがあります。
緊張状態にある猫は、自分を守るために攻撃的になることがあります。
このような様相を呈するのは、病院帰りではよくあることです。
主な世話を担当している飼い主ですら攻撃対象になることも。
特にキャリーケースから出した直後は、猫が周囲に敏感になっているため、落ち着くまでは距離を保ちましょう。
無理に撫でたり構ったりせず、安心できるスペースでひと息つかせるのが大切です。
基本的に寄り道はしない
また、病院から帰ってくるあいだに寄り道はしないようにしましょう。
病院に行った時点で、猫には相当な負担がかかっています。
さらに寄り道して帰宅が遅れるなどして、余計なストレスをかけるのは避けたいところ。
また、飼い主が猫を残して降りてどこかへ行くといったことも避けたいです。
余計な負担をかけないためにも、寄り道はしないようにしましょう。
猫と病院でのストレスに関するよくある質問
この記事では猫の病院に関係したストレスに関して解説しました。
ここではよくある質問に回答します。
- 体調が悪ければ病院には行かないほうがよい?
- 病院から帰ったらご飯を食べないときは?
- 病院後に猫に嫌われることはある?
- 猫が病院のストレスで死ぬことはある?
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
体調が悪ければ病院には行かないほうがよい?
体調が悪いときこそ病院に行くべきです。
病院に行くことでストレスは多少かかりますが、そのまま放置するほうがはるか危険。
猫は、食欲不振や下痢、嘔吐などに代表される、心身の不調を隠す動物です。
見た目以上に重大な疾患を罹患している場合もあるため、「ストレスをかけたくないから行かない」というのはあやまりと言えるでしょう。
ストレスがかかることを理解しつつも、すみやかに病院へ連れて行くのが大切です。
特に猫は腎臓が弱く、トイレが上手にできない、まったくいかないなどの兆候を見せるケースが多いです。この点を覚えておけば、腎臓疾患を発症した際、スムーズに対応できるかもしれません。
病院から帰ったらご飯を食べないときは?
病院から帰ってきてご飯を食べないのであれば、まずは精神的に落ち着くのを待ちましょう。
しばらく待っても食べそうになければ、好物やおやつを与えます。
基本的に好きなものであれば、問題なく食べ始めるでしょう。
ちゅーるなどもおすすめです。

一方で無理やりに追いかけて食べさせるのは避ける必要があります。
日が明けても食欲が戻らないなら、何らかの障害が考えられます。ただちに動物病院へ連れて行くようにしましょう。
病院後に猫に嫌われることはある?
病院後に猫に嫌われることは大いにあります。
通院のストレスは、病院での処置や移動中の経験によりますが、猫がかならずそのように判断できるとは限りません。
連れて行った飼い主のせいだと考え、怒ったり、そっけない態度を取ったりすることはあり得ます。
しかし、これは一時的なものであることがほとんどであり、放っておけばそのうち機嫌を直します。
もし改善しない場合は、そもそもの信頼関係が希薄だったのかもしれません。スキンシップを図る、可愛がるなどして、仲良くなれるようにするのがよいでしょう。
関連記事▶︎猫が威嚇してしまう心理は?攻撃される仲良くなる方法を解説
猫が病院のストレスで死ぬことはある?
病院のストレスが、死亡の直接の原因になることはほとんどありません。
ストレスがあるとはいえ、通常は生死には関係しません。
しかし、持病があったり、極端に高齢だったりした場合、そのストレスが原因で容体を悪くすることはあり得ます。
したがって、通院時には本記事で紹介したようなポイントを意識し、できるだけ負担がかからないようにするのが大切です。
とはいえ、猫が死亡に至るまでは、以下のように毛が抜けるなどの兆候に気づくはずなので、可能性としては高くありません。
長崎からの保護依頼、飼い主死亡で身内の方に外に出され家は釘付け、外に出された3匹の高齢猫貴子さんはストレスで痩せて毛が抜け落ちてしまいました。今は綺麗です。 https://t.co/9bdEOAoKrV
— 浩代 (@hiroyo314) February 4, 2024
まとめ

本記事では、猫の通院中のストレスに感じて解説しました。最後に重要なポイントをおさらいしましょう。
- 猫は通院そのものに強いストレスを感じやすい
- キャリーケースに慣れさせ、落ち着いた環境で準備することが大切
- 移動中は揺れや外の刺激を減らすのがポイント
- 必要に応じて、フェロモン剤の使用も検討に
- 診察中はタオルで包む、飼い主が声をかけるなどで安心感を与える
- 帰宅後は怒っている猫に無理に触れず、落ち着くまで静かに見守る
- 一時的に嫌われたり怒られたりするが、すぐに落ち着くケースが大半
- 通院ストレスが直接命に関わるケースはまれで、ほとんどは適切な配慮で防げる
猫にとって、病院への通院は大きなストレスです。とはいえ、病気を治すために通院は避けられません。
そのうえでも、飼い主がストレスがかからないように工夫するのが大切といえるでしょう。
とはいえ、飼い主にもできる配慮には限界があり、またストレスが原因で死亡したり重大な病気を発症したりするリスクはさほど高くありません。
あまり気負いすぎず、できる範囲で対策しましょう。
関連記事