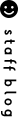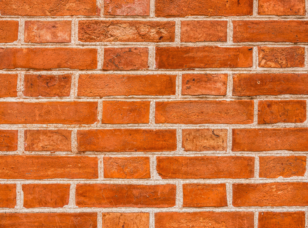2025.03.31
猫が悪いことをしたときの叱り方としつけの基本姿勢

- 猫が悪いことしたらどう叱ればよい?
- 言葉で叱って理解できるのか?
- トイレなどを覚えてくれない
このような疑問や悩みを持っている人は多いのではないでしょうか?
猫が悪いことをしたときは、正しい叱り方で注意するのが大切です。言葉は通じませんが、態度を示せば、猫は学習できます。
しかし「怒鳴りつけない」「体罰を与えない」などのポイントをおさえる必要があるでしょう。
本記事では、猫が悪いことをしたときの叱り方や基本姿勢、信頼関係を保ちながらしつける方法などを解説するので、参考にしてください。
もくじ
猫が悪いことをしたときの叱り方と基本姿勢

まずは、猫が悪いことをした場合の叱り方と基本姿勢をおさえましょう。
- 怒鳴りつけず一般的なトーンで叱る
- 体罰はいっさい与えず態度で示す
- 猫を追いかけず真剣に注意する
- 「叩くふり」をせず言葉と目線でしつけをする
猫が悪いことしたとき、感情に任せて叱ったり、手荒なことをしたりするのはいけません。正しい叱り方と基本姿勢に沿って、叱るのが大切です。
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
怒鳴りつけず一般的なトーンで叱る
まず、怒鳴りつけるのではなく、一般的なトーンで叱るようにしましょう。
たとえば、「こら」「そんなことをしてはダメでしょう」などと、恐怖を感じない程度の声色やトーンが基本です。
大声で怒鳴りつけると、猫は恐怖を感じ、飼い主に対して信頼できなくなります。したがって、感情的に怒鳴るなどせず、一般的なトーンで叱るのが大切。
ただし、猫や人の安全や生命にかかわるような悪さをした場合は、強い口調で注意したほうがよいでしょう。
体罰はいっさい与えず態度で示す
また、体罰はいっさい与えず、態度で示すようにしましょう。
体罰を加えられたとしても、しつけに対する理解度を高められるわけではありません。むしろストレスを感じて別な悪さをしたり、飼い主になつかなくなったりします。
また、猫の体は想像以上にデリケートです。体罰を与えることで、怪我をするかもしれません。
厳しすぎるしつけや体罰による悪影響は、多くの保護猫団体も懸念しています。したがって体罰はいっさい与えず、態度でしつけることを徹底しましょう。
猫を追いかけず真剣に注意する
どのような事態があっても、猫を追いかけるのはやめましょう。遊びの範疇だと誤解され、きちんと学習できないからです。
猫は、基本的に追いかけっこするのを「楽しい遊び」と認識します。
飼い主が注意したり、叱ったりする目的でも、追いかけてしまうと、猫は「一緒に楽しんでいる」と判断するかもしれません。
そうすると、猫のしつけはうまくいかなくなります。
どのような事態があっても、猫を追いかけないようにしましょう。
「叩くふり」をせず言葉と目線でしつけをする
また、「叩くふり」など、危害を加える行為と誤解されるようなことはしないようにしましょう。
猫は、手の動きに対して敏感で、叩こうとすると恐怖を感じます。そうすると、飼い主に対して恐怖を感じ、信頼関係にも影響が出るかもしれません。
体罰を与えるそぶりはいっさい見せず言葉と目線だけでしつける必要があります。
猫が悪いことをしたらどう叱る?飼い主との信頼関係を築きながらしつける方法

- 悪いことをしたらその場でただちに叱る
- よいことをしたらその場でただちに褒める
- 「悪いことをするとばちが当たる」ことを教える
- 叱ることは一貫して叱る
- しつこい要求はひたすら無視をする
- ストレスが発生しない環境を整える
もっとも大切なのは、猫が悪いことをしたら、その場でただちに叱ること。それを改善したら、やはりただちに褒めることです。
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
悪いことをしたらその場でただちに叱る
まず、悪いことをしたら、その場でただちに叱るようにしましょう。
猫は記憶力がさほどよくなく、時間が経ってから注意しても、「叱られた原因と事実」をうまく結び付けられません。
そうすると、ただ単に「怖い思いをさせられた」と感じられ、しつけはできていないのに嫌な思いだけはさせてしまいます。
したがって、悪いことをしたら、その場でただちに叱るのが大事です。
時間が空いてしまったら、その件に関しては叱らないほうがよいでしょう。
よいことをしたらその場でただちに褒める
また、よいことをしたらその場でただちに褒めましょう。
猫は、「そのあとに、どのようなよいこと、悪いことがあったか」で、行動を学習する傾向があります。
悪いことをやめたり、一般に「えらい」とされることができたりしたときは、ただちに褒めてあげましょう。
「こうすると、なにかしら褒められた」と記憶し、また褒められるために行動を改善してくれます。
言葉で褒めるのはもちろん、気持ちよいところ撫でるのもよいでしょう。
また、チュールをはじめとしたご褒美を与えるのも効果的です。
「悪いことをするとばちが当たる」ことを教える
「悪いことをするとばちが当たる」と教えるテクニックも、効果的です。
これは、悪さをしたとき、飼い主が直接叱ったり叩いたりするのではなく、猫に気づかれないようで「ばち」を与える方法。
たとえば、悪さをしようとしたときに驚かしたり、あまり触られたくないところを触ったりします。
また、しつけスプレーを使って学習させる方法もあります。

出典:Amazon
しつけスプレーとは、猫が嫌う苦味や香りを含んだスプレーです。
悪さをしようとしている、したあとで噴霧し、「悪いことをするとばちがあたる」と学習させられます。
必要に応じて、しつけスプレーを使うとよいでしょう。
叱ることは一貫して叱る
また、叱ることは一貫して叱るようにしましょう。
同じことがらに対して、あるときには叱り、あるときは叱らない、などの行為は避けるべきです。
いわゆる「ダブルスタンダード」と呼ばれるしつけは、猫を混乱させる要因。
人間でも、ダブルスタンダード型の指導を受けると、自分が何をすればよいのかわからなくなるといわれます。言葉がわからない猫は、なおのこと善悪の判断をつけられなくなるでしょう。
したがって、できる限り「叱ることは叱る」ように意識しましょう。
しつこい要求はひたすら無視をする
しつこい要求は、叱るよりも、ひたすら無視する形でしつけます。
猫は、自分の要求が通らないとき、とにかく鳴いたり、爪を立てたりして、わがままを叶えてもらおうとします。
もちろん、叶えられるわがままは叶えてやってもよいでしょう。しかし、猫の望みのすべてを叶えられるわけではありません。
そのような場合は、叱るのではなく「無視をする」のが重要です。無視すれば、「何を言っても、このわがままは叶わない」と学習できます。
ストレスが発生しない環境を整える
問題行動を避けるためには、ストレスが発生しない環境を整えるのが大切です。
悪さの原因が、すべて猫にあるわけではありません。ストレスを感じやすいがゆえ、問題行動に走っているケースがあります。
したがって悪さをさせないためには、ストレスフリーな環境を整えるのが大切です。以下の点を見ながら、環境を整備しましょう。
- 室温を27〜30度で調整する
- 上下運動ができる環境を整える(キャットタワーの設置など)
- 清潔なトイレを用意する
- 騒音などが聞こえにくようにする
- 日差しを浴びたり、外の景色を観察できたりする場所を作る
- 十分なフードと水、おやつを用意する
可能な限りの環境整備で、猫の問題行動を予防しましょう。
【シーン別】猫に悪いことをさぜずしつけを覚えさせる

猫の悪さとは、トイレのルール違反やテーブルの昇降など多岐にわたります。特定の問題行動を改善できる悩んでいる人も多いでしょう。
ここでは、シーン別での猫の悪さに対するしつけ方や、問題行動を改善する方法を解説します。
- トイレのルール違反
- テーブルの昇降
- 噛み癖
- ものに対するいたずら
- 爪研ぎ
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
トイレ|清潔なトイレを提供して少しずつ覚えさせる
トイレのしつけでもっとも大切なのは、清潔な環境を整えること。
猫は基本的に、トイレのルールを守るのが得意な生き物です。それでもルールが守れないなら、トイレが不潔になっているかもしれません。
猫は不潔な環境を嫌い、トイレがそうなっているなら、そこで排泄するのを避ける傾向があります。猫砂を頻繁に取り替えるなどして、常に清潔な環境を保ちましょう。
また、トイレを複数設置し、汚れにくくするのもひとつの方法です。
近年では自動で清掃がおこなわれる自動トイレも流通しています。余裕があれば導入しましょう。
テーブルに登る|登ったり下りたりしたらバチを当てる
テーブルに関しては、登ったときにただちに下ろし、叱りましょう。これを繰り返せば、「テーブルには登ってはいけない」ことを学習します。
しつこく登るようなら、先ほど解説した「バチを当てる」のがおすすめ。しつけスプレーなどを撒いて、「テーブルに登ると嫌なことが起こる」のを学習させましょう。
噛み癖|おもちゃを与えつつ冷静に対応する
噛み癖に関しては、おもちゃを与えつつ冷静に対処するのがポイントです。
何かを噛むのは猫の性質上仕方がないこと。しかし飼い主の手足や家具などを噛まれると困るので、「噛む用のおもちゃ」を与えるのがおすすめ。
たとえば以下のようなものを与えましょう。

出典:Amazon
噛み癖に関しては、飼い主や家族のけがにもつながる習慣です。大きなダメージを負う前に、優先的にしつけるのがおすすめです。
ものに対するいたずら|犯行の瞬間に叱って学習させる
ものに対するいたずらに関しては、犯行の瞬間に叱るのが基本です。高価、重要なものを傷つけて場合は、強めに叱るのがよいでしょう。
ただし、いたずらしてからしばらく経ったあとでは、叱っても効果がありません。猫が覚えているくらいのタイミングで、きちんと注意しましょう。
爪研ぎ|爪研ぎグッズを与えてやめさせる
家の柱などで爪研ぎをするなら、爪研ぎクッズを与えましょう。猫が爪を研ぐのはきわめて一般的な習性であり、させないわけにはいきません。
したがって、爪研ぎを禁ずるのではなく、家の柱などと比較して快適に爪を研げる環境を与えるのがポイントです。
もっともシンプルなのは、爪研ぎ用の猫グッズを与えること。

出典:Amazon
爪研ぎができるグッズを置いておけば、基本的に問題は解決できます。それでも家の柱などで爪を研ぐなら、きちんと叱りましょう。
そして、爪研ぎグッズの前に連れて行くのを繰り返せば、しだいに改善されるでしょう。
猫のしつけに関するよくある質問

本記事では、猫のしつけに関して解説しました。
ここでは、よくある質問に回答します。
- 猫は悪いことをした自覚があるのか?
- いたずらをするのはわざとなのか?
- 猫が叱って逆ギレするときは?
- 猫は叱られると落ち込むのか?
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
猫は悪いことをした自覚があるのか?
ほとんどの場合、猫に悪いことをした自覚はありません。
しかし、何度もダメだと叱られたことをやってしまった場合、「これは怒られる」程度には思っているといわれています。
怒られるのを避けるため、何かをやらかしたあとは、どこかに隠れていることも。自覚しているように見えるなら、やさしく叱る程度におさえるとよいでしょう。
いたずらをするのはわざとなのか?
猫がわざといたずらをすることはあります。
たとえばパソコンや新聞紙を見ていると、目の前に座って注目を浴びようとすることがあります。
それと同様に、いたずらで注目されようとしているケースは少なくありません。
わざといたずらするのを防ぐには、普段からのスキンシップやコミュニケーションが重要です。猫がさみしくならないようにかまってあげましょう。
猫が叱って逆ギレするときは?
猫が叱って逆ギレするときも、かわらず冷静な態度で叱るのが大切です。
逆ギレは、人間社会にでは相当な批判を受ける行為です。しかし、猫に対してそのルールを強いるのは現実的ではありません。
逆に怒る場合でも、常に落ち着いて対処する必要があります。
また、逆ギレに関しては、飼い主のしつけ方に問題があるかもしれません。たとえば叩いたり、怒鳴りつけたりすると、怖がって反撃、つまり逆ギレするケースがあります。
したがって、体罰や大声を用いず、冷静な態度でしつけるのが大切です。
猫は叱られると落ち込むのか?
猫は叱られると、状況によっては落ち込むことがあります。言葉は理解できないものの、トーンや表情から叱られているのを自覚し、しょんぼりしたようなようすをみせます。
ただし、人間ほど正確に叱られているのを理解できるわけではありません。
毅然とした態度で叱られないと、単に「かまってもらえた」などと感じることがあります。だからこそはっきりと「叱られている」とわかる態度で叱らなければいけません。
まとめ

本記事では、猫が悪いことをしたときの叱り方を解説しました。
最後に重要なポイントをおさらいしましょう。
- 猫が悪いことをしたときは、一般的なトーンで叱るのが大切
- 体罰を与えたり、危害を加えるふりを見せたりするのはNG
- 悪いことをしたらただちに叱る
- よいことをした場合も、ただちに叱る
- 「悪いことをするとばちが当たる」と学習させるのは有効なテクニック
- トイレのルール違反や噛み癖などは、状況に応じてしつけ方を変える
- いずれの場合も、猫に恐怖を与えず、毅然とした態度で叱るのが重要
猫にとって、人間は体が大きく、基本的には恐怖の対象になり得ます。だからこそ恐怖感を必要以上に抱かせず、愛情を持ちながらもしっかりとしつけをするのが大切。
本記事を参考に、猫との信頼関係をキープしながら、毅然としたしつけを実施しましょう。
関連記事